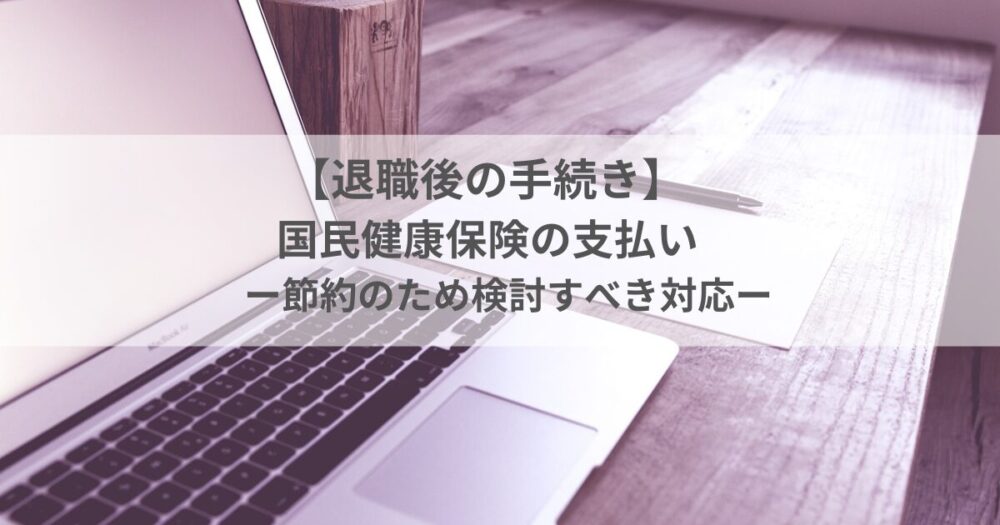以前記載したように、退職後の健康保険は「前年の収入が影響する退職1年目は任意継続被保険者になり、収入が減少する退職2年目からは国民健康保険に加入する」対応です。
「【退職後の手続き】確定申告 ー退職2年目の対応は必要?定額減税は?ー」の記事で記載した通り、国民健康保険料の計算には住民税の申告が必要であるため、確定申告で対応しました。
「【退職後の手続き】国民健康保険への切り替え ー変更手続きは?ー」の記事に記載した通り、2024.03.31で任意継続の健康保険を終了し、国民健康保険に加入しました。ただ、支払金額は確定申告を踏まえて6月に決定されるとのことで、当時はわかりませんでした。
支払いはどの程度の額になるか納付書の郵送を選択し、実際に届いたので内容を記載します。 大きく節約できる可能性がありますので、退職を考えている方にはご参考になるかもしれません。
あわせて読みたい


【退職手続き】お金の手続きガイド|退職金、年金、財形貯蓄、社会保険、個人で入る保険の整理術
一度ブログにアップした記事で退職前の手続きを纏めました。 お盆前に出向元に退職の連絡した後、9月位から12月末の退職に向けた手続きの書類が届き始めました。 期限の…
あわせて読みたい

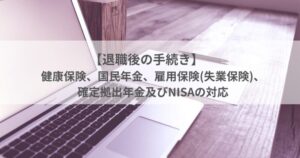
【退職後の手続き】健康保険・年金・失業保険・iDeCo/NISA|社会保険の切り替え完全ガイド
一度ブログにアップした記事で退職後の手続きを纏めました。 2023年の12月末で恙なく退職しました。 退職後の手続きを記載していきます。 これから退職される方の手続き…
あわせて読みたい

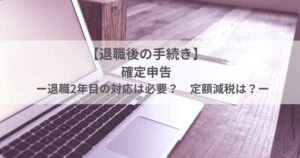
【退職後の手続き】確定申告 ー退職2年目の対応は必要?定額減税は?ー
退職2年目は確定申告は必須ではありませんでしたが、退職後の健康保険は「前年の収入が影響する退職1年目は任意継続被保険者になり、収入が減少する退職2年目からは国民…
あわせて読みたい

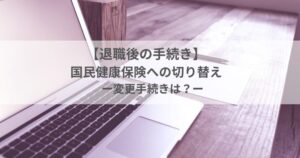
【退職後の手続き】国民健康保険への切り替え ー変更手続きは?ー
以前記載したように、退職後の健康保険は「前年の収入が影響する退職1年目は任意継続被保険者になり、収入が減少する退職2年目からは国民健康保険に加入する」対応で進…
目次
国民健康保険の納付金額
- 届いた封筒に保険料は所得控除の社会保険料控除の対象である旨、記載されていました。
- 国民健康保険料決定通知書が同封され、2026.03までの毎月の納付金額、医療、後期高齢者、介護の保険料の内訳が記載されていました。
- 国民健康保険料のお知らせが同封され、計算式、軽減・減免、支払いについての案内がありました。
- 郵送で対応できる口座振替・自動払込依頼書と2026.03までの毎月の納付書が同封されていました。

痛みを実感するためにしばらくは納付書で対応しようと思います・・・
- 年間の納付金額は、昨年の退職1年目の3割以下になっていました。昨年は給与収入が無かったので、扶養家族分を考慮しても国民健康保険の方が、任意継続より安くなると自分で試算していました。よくわからないので幅をもって試算していましたが、一番安い試算にほぼ近く、数十万円節約できたと思います。
- 退職前に給与収入がある程度あり、退職後は収入が乏しい方は任意継続を1年で変更して国民健康保険に変更する対応もおすすめです。



その際は住民税の申告をお忘れなく!
国保(国民健康保険)の健診
- 同じくらいの時期に国保の健診のお知らせが届きました。
- 企業の健康保険は補助があり、人間ドックが割安で受けられるので昨年の任意継続の間に受けておきました。
- 自治体によってどの程度異なるのかわかりませんが、大阪市の場合は国保でも60歳、65歳などの5年刻みの年齢で、人間ドックが無料です。
- 上記の無料の年齢以外は、10,000円で人間ドックを受けられるとのことです。



企業の健康保険の補助より費用はかかりますが有難いことです!
- 働いていた頃、毎年受けていた健康診断は、特定健診として無料で受けられます。
- 退職するまで知りませんでしたが、がん検診もいろいろあるようです。



今年は特定健診にして、2年に1回人間ドックを受ける対応を考えています!
まとめ
- 「前年の収入が影響する退職1年目は任意継続被保険者になり、収入が減少する退職2年目からは国民健康保険に加入する」対応で退職2年目の健康保険料は3割以下になり、数十万円の節約になりました。
- 企業の健康保険には補助があるケースも多いので、退職2年目まで任意継続被保険者となることも考えられますが、国保の健診も大きく見劣りするような内容ではありませんでした。
- 退職前に給与収入がある程度あり、退職後は収入が乏しい方は任意継続を1年で変更して国民健康保険に変更する対応もおすすめです。



扶養家族の数、退職前の給与収入や退職1年目の収入によって節約できる金額は個別に変わって来るとは思います。
参考
- 私がこのブログでよく引用させて頂いているRanpaさんのブログ「45歳でアーリーリタイアして資産生活」の更新頻度が変わるようです(RanpaさんからリンクOKの許可を頂きました)。
- “アーリーリタイアに至る記録を残すことと、アーリーリタイアを目指す人にとってこんなブログが欲しかった。そんなことを考えたことがブログを始めたきっかけでした。”と記載されていますが、私もブログに「退職手続き」のカテゴリーを作ったのは同じ気持ちです。
- 多くの当事者にとっては生涯に1度のことだと思いますが、手続きが分業化されており多岐にわたるため全体像が掴みにくく、その割に相互に連携していることが多いです。



今回の国民健康保険の支払いにしても、任意継続を選ぶかどうか、切り替え、確定申告と2年がかりの手続きです。
- 退職の具体的な体験談はRanpaさんのブログを参考にさせて頂いたところも多く、お陰様で私も現状無事に退職生活を送れています。
- Ranpaさんのブログの「退職手続き」のカテゴリーは退職を考えておられる方におすすめです。



Ranpaさんありがとうございました!今後の記事も楽しみにしております!
無事に退職手続きを終えたあとも、「ではその後、どんな生活になるのか?」はなかなか想像しにくいものです。私自身の退職後の生活や、やりたいことの変化は以下のカテゴリーに纏めています。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。